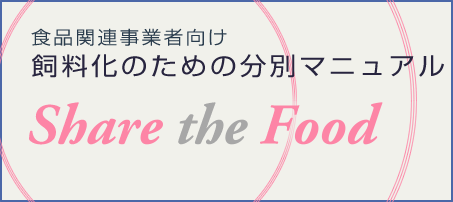7月24日(木)2025年度ゼロエミッション研究会第2回勉強会を開催
ゼロエミッション研究会
あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システム=「ゼロエミッション」
当財団では、ゼロエミッションの実現に向けて、2017年より食品小売業・外食産業の店舗から発生する廃棄物(特に食品循環資源)の発生抑制・資源循環・適正処理の手法を学ぶ場として、「ゼロエミッション研究会」を開催しています。
第2回ゼロエミッション研究会
7月24日(木)に今年度2回目となるゼロエミッション研究会を開催しました。40社86名の方にZOOMとのハイブリット勉強会にご参加頂きました。「2023年度食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の実施率」について、東京農業大学名誉教授/SEF顧問の牛久保明邦氏に、「食食品ロス発生メカニズム-経済学的分析を」について、叡啓大学副学長・学部長・特任教授/神戸大学名誉教授/NPOごみじゃぱん代表理事の石川雅紀氏に、「割りばしのアップサイクル ChopValueの取り組み」について、ChopValue Manufacturing Japan株式会社代表取締役ジェームス・ソバック氏にご講演いただきました。
- 「2023年度食品廃棄物等の発生量及び再生利用等の実施率」 東京農業大学名誉教授/SEF顧問
牛久保 明邦氏
2023年度食品廃棄物等及び食品ロスの年間発生量について、食品産業における食品廃棄物等の発生量の推移について、事業系食品廃棄物等・食品ロスの発生量の業種別内訳について、事業系食品ロスの業種別発生量の推移について、SDGs目標12・ターゲット12.3 2030年度までの食品ロス削減目標について、また、2023年度 食品循環資源の再生利用等の実施実績ついて、食品産業における再生利用等の実施率の推移について、食品リサイクル法における再生利用手法の業種別内訳についてお話をいただきました。

- 「食食品ロス発生メカニズム-経済学的分析を」 叡啓大学副学長・学部長・特任教授/神戸大学名誉教授/NPOごみじゃぱん代表理事 石川 雅紀氏
世界全体や日本の食ロスについて、食品ロスと温暖化問題について、食ロスはなぜ出るのか、食ロスが発生する理由、食品ロスを減らす対策についてお話いただきました。特に食品を減らす対策として、食品ロス削減には啓発だけでは不十分・食品ロスが持続的に減っていく仕組みが必要・原因が不確実性なので、情報交換、情報共有が有益、コミュニケーションが有効、対策としてフードシェアリングを利用したり、見切り品を値引きして販売したりなど。また、賞味期限・消費期限内の食品が捨てられる3分の1ルールについて、2分の1に緩和すると食品ロスが4万トンほど削減されたため、賞味期限の大括り化が進んでいるなどをお話しいただきました。
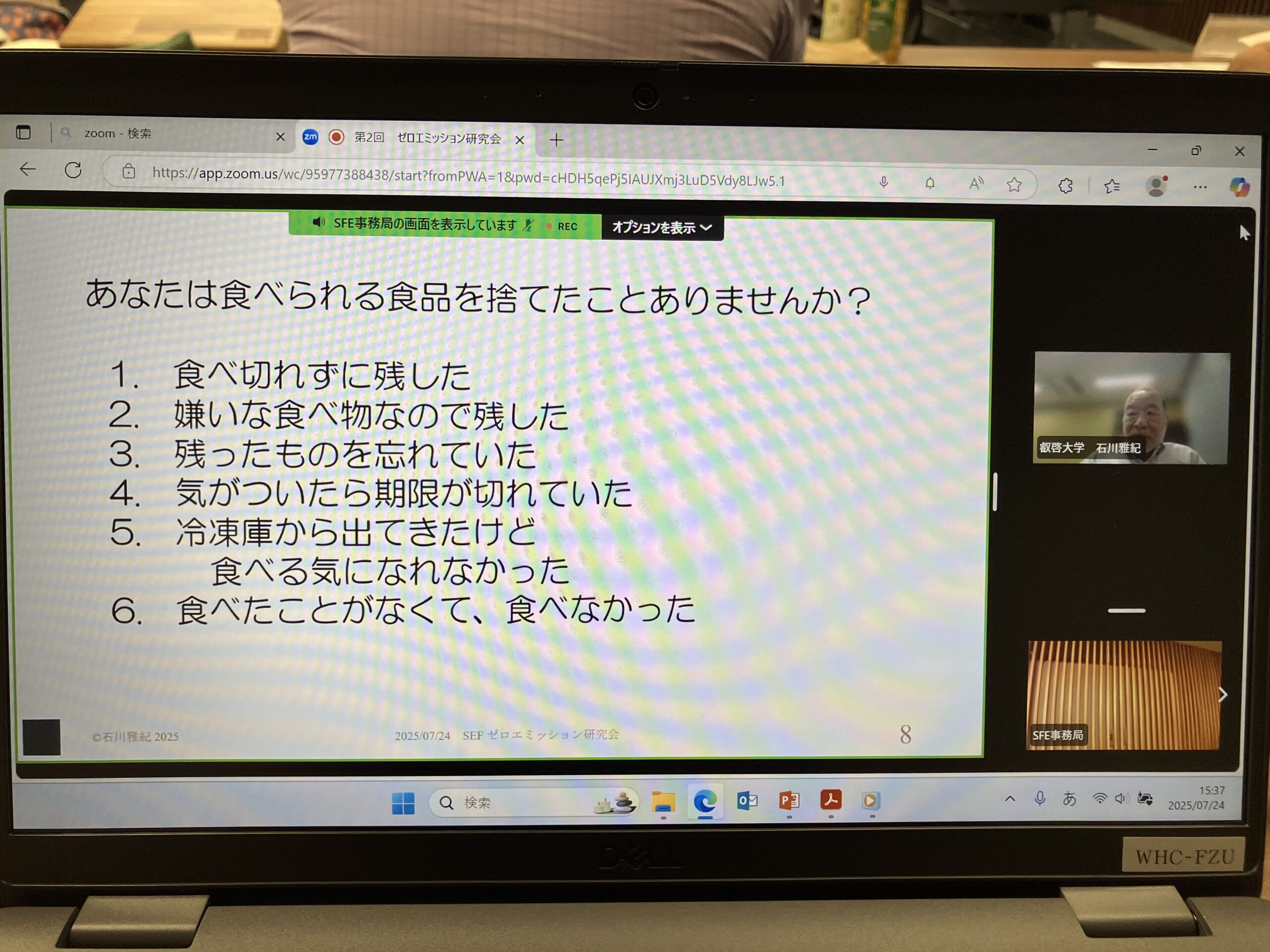
- 「割りばしのアップサイクル ChopValueの取り組み」 ChopValue Manufacturing Japan株式会社 代表取締役
ジェームス・ソバック氏
日本ではおよそ200億膳の割り箸が廃棄されている。使用済みの割り箸を地域ごとに回収し、地域の「小規模工場(マイクロファクトリー)」で再生素材にアップサイクルを行っている。これまで活用されていなかった割り箸という資源を、家、レストラン、企業向けに、品質やデザインを妥協することなく、地球にやさしい木材代替製品へとアップサイクルしてきた。2025年 4 月には、日本初となるフラッグシップ・マイクロファクトリーを神奈川県川崎市に正式オープンし。地域で回収した使用済み割り箸を再資源化し、高品質な家具やインテリアへとアップサイクルしている。今後全国に展開予定の複数拠点の先駆けとなるこのマイクロファクトリーは、地域主導かつスケーラブルな分散型生産ネットワークの一翼を担い、日本における循環型経済の実現に貢献していく。オフィス・ホスピタリティ・インテリアに使用されている。森林伐採を減らしCO2排出量も減らしている。この取り組みを丸亀製麺と行っているなどをお話しいただきました。

参加企業からの声
「食品ロスは減少傾向にはあるもののまだまだ量としては多く、企業からの排出だけではなく家庭からの排出も多いので、食品ロスを発生させない商品開発や啓発活動なども必要だと改めて感じました。」「再生利用法の業種別内訳について、昨今の廃油の有価買取増加によって「廃棄物」でなくなる廃油が増えることによる影響について知りたい。特に表面的にリサイクル率が下がるなどの影響や補足できなくなる廃油の量が増えるのではないかと思う。」「廃家庭系の食品ロスについて、改めて考えることが少なかったので、新しい視点や気づきがありました。一人暮らしで自炊をしていると、野菜の外葉や種、魚の骨以外は自分の好みで好きなように食べていたので、食品ロスはほぼでません。しかし家族が多いと、それぞれの好みや食べられる量、体調不良などによっても食品ロスが発生してしまうなど、やむを得ない部分が多いと感じました。事業系は様々な企業が、努力をされて確実に成果を出せていますが、家庭系は個々で対応するにはかなり難しいので、何か簡単にトライできる取組みがあればご教授ください。」「食品ロスの発生原因を「不確実性」という定義は興味深かった」「今まで、食品のアップサイクルばかり目が行っていましたが、わりばしもアップサイクルができるのだと、新しい視点でのお話にとても興味深かったです。弊社の場合は飲食店とは違い、配布したわりばしは店舗とは別の場所で使用いただくことの方が多いので回収量としてはあまりないかもしれませんが、もしこれができたら面白そうだと思いました。また、弊社の場合は木ではなく竹でできたわりばしを配布しておりますが、竹素材のものでも同様にリサイクルが可能なのかお伺いしたいと思いました」「わりばし自体を減らす方向で考えているので、少し疑問は残りましたが、環境的に問題なく伐採材の無駄を省けるということであれば、使うからには、今回のアップサイクルは魅力的な話かなと思いました。」などとご意見をいただきました。
- 2025年度 ゼロエミッション研究会
2025年度のゼロエミッション研究会は、9月18日(木)を予定しております。
ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご参加の程お待ちしております。
- 2025年8月14日
- カテゴリー: イベント・ボランティア報告, 事業活動報告, 資源循環事業
- タグ: セミナー