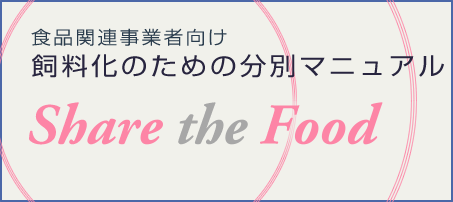5月29日(木)2025年度ゼロエミッション研究会第1回勉強会を開催
ゼロエミッション研究会
あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄物を一切出さない資源循環型の社会システム=「ゼロエミッション」
当財団では、ゼロエミッションの実現に向けて、2017年より食品小売業・外食産業の店舗から発生する廃棄物(特に食品循環資源)の発生抑制・資源循環・適正処理の手法を学ぶ場として、「ゼロエミッション研究会」を開催しています。
第1回ゼロエミッション研究会
5月29日(木)に今年度1回目となるゼロエミッション研究会を開催しました。45社90名の方にZOOMとのハイブリット勉強会にご参加頂きました。基調講演として「食品リサイクル法の基本方針等の見直し 食品循環資源の堆肥の土壌への有効性など」について、東京農業大学准教授の入江満美氏に、「食品ロスに新たな価値を」について、株式会社日本フードエコロジーセンター代表取締役の高橋巧一氏にご講演いただきました。
- 「食品リサイクル法の基本方針等の見直し 食品循環資源の堆肥の土壌への有効性など」 東京農業大学 准教授
入江 満美氏
栄養は土壌の95%から出来ていて、残りの5%は魚介類、土壌は薄く脆弱、粒子の細かさではない、地衣類(コケ等)が土壌の始まり、小さな生物の餌になり、排泄物が栄養となり繰り返していく、土壌が1センチ出来るのに世界平均で500年ぐらい、日本は高温多湿なので100年ぐらいだが非常に時間がかかる、土壌に有機物を還元すると植物残渣は微生物の食料、微生物の排泄は植物の肥料に、死後は土壌の炭素プールへ、有機物は土壌の炭素プールへついて。また、世界の食料生産量の3分の1は廃棄され、世界の緑両生産量の45%は破棄されている、食品ロスと食品廃棄を2030年までに半減することを国際目標としている、食品リサイクル法の基本方針目標値見直し議論の方向性で重要視された具体的な施策として、優良事例の情報提供を通じた地方公共団体との連携促進。食品リサイクルに関する情報発信の強化。登録再生利用事業者の確保と活用促進。食品廃棄ゼロエリアの創出等を通じた先進的取り組みの整理と横展開。外食産業における再生利用等の促進のためのマニュアル普及や関係者との連携強化が挙げられた、事業系食品ロスについて、従来の「2000年度比で2030年度までに半減」の目標を前倒しで達成したことを踏まえ、新たに「2000年度比で2030年度までに60%削減」という目標が設定、食品関連事業者への新たな取り組み要請として、未利用食品の提供:まだ食べられる食品を、貧困や災害などで必要としている人々に提供する活動(フードバンク等)への参加を促進。商慣習の見直し:「3分の1ルール」などの商慣習見直し、食品廃棄物の発生抑制を図る。情報開示の推進:食品関連事業者が行う食品ロス削減の取り組みや、フードバンク等への提供量を、有価証券報告書や統合報告書、インターネット等で情報提供するよう努める。再生利用等実施率の新たな目標設定として業種別の目標値(2029年度まで):食品製造業:95%(変更なし)、食品卸売業:75%(変更なし)、食品小売業:65%(前回より5%増)、外食産業:50%(変更なし)とのお話をいただきました。

- 「食品ロスに新たな価値を」 株式会社日本フードエコロジーセンター 代表取締役
高橋 巧一氏
食品ロスが引き起こす問題について、食品調達による環境破壊での地球温暖化への影響、食品ロス問題における世界動向と日本の情報発信ついて、また、エコフィードとその意義(飼料自給率)、エコフィードの原料となる主な食品循環資源、エコフィード製造作業フローについて、お話いただきました。日本フードエコロジーセンターで新たなビジネスモデルを構築し、食品関連事業者と養豚事業者の双方がコストダウン、食品廃棄物を焼却処分している自治体の税金軽減にも寄与しているとのお話をしていただきました。

参加企業からの声
「前半の堆肥成分の有効メカニズムや土壌の解説について参考になりましたが、もう少し後段の食リ法の見直しについての背景や解説、各関係者に求められるレベル感などしっかりと伺いたかったです。」「土壌等に関して全く知らない領域のお話でしたので大変勉強になりました。食品リサイクルに関しての変更点もお話いただけて、飲食は数値的に今回は変更なさそうですが今後も要注意していこうと思いました。」「廃棄物、障がい者支援など、複合的に取り組みビジネスとサステナを共存させている点に特に興味がわきました。自社でもフードロスをなくすという強い気持ちで削減を進めていきたいと感じました。」「ゼロエミッションを進めることが日本の食糧自給里を改善していくため非常に重要なミッションと感じました。このような施設が弊社の出店エリアである北関東にも拡大されることを切に期待します。」などとご意見をいただきました。
- 2025年度 ゼロエミッション研究会
2025年度のゼロエミッション研究会は、7月24日(木)を予定しております。
ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご参加の程お待ちしております。
- 2025年8月14日
- カテゴリー: イベント・ボランティア報告, 事業活動報告, 資源循環事業
- タグ: セミナー